太宰府市の生活に役立つ便利情報
福岡県太宰府市 生活ハンドブック:住民のための行政・生活情報
序章:太宰府市での生活を始めるにあたって
0.1 構成と利用方法
福岡県太宰府市に居住する住民の皆様に対し、日常生活の円滑な運営と緊急事態への迅速な対応を支援するための実用的な情報を提供するものである。太宰府市は、歴史的な景観と都市生活の利便性が融合した地域であり、その行政サービスや生活インフラは、福岡都市圏の広域連携体制の下で運営されている。
市民生活に必要な5つのコア領域、すなわち行政手続きと子育て支援、ごみ処理とリサイクル、交通アクセスと公共施設、医療・救急体制、そして防災・安全対策に基づき、体系的に構成されている。各章は、単なる手続き案内や施設紹介に留まらず、規則の背景や地域の連携構造を専門的な視点から解説しており、居住者が日々の生活や重要なライフイベントを迎える際に、迅速かつ的確に参照できる実用的な指針となることを目指している。
第1章:行政手続きとライフイベント支援
1.1 転入・転居時に必要な主要手続きと市役所窓口
太宰府市での生活を始めるにあたり、市民は太宰府市役所にて複数の重要手続きを完了させる必要がある。市役所の「申請・手続き」カテゴリには、戸籍・住民票・各種証明、税金、国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金、介護保険といった市民生活の根幹に関わる分野の手続き情報が集約されている 。
これらに加え、市は高齢者福祉、社会福祉、障がい者福祉、生活支援、子育て支援、母子の健康、学校・生涯学習など、市民の多様なニーズに応じたサービスを網羅的に提供している 。市民は、市ホームページのカテゴリメニューを通じて、必要な行政情報を検索することが可能である。
行政手続きにおいては、制度の最新情報に留意することが極めて重要である。例えば、市は2025年9月1日更新情報として、戸籍にフリガナが記載される制度変更の情報を公開しており、また、定額減税不足額給付金や各種予防接種に関する最新の案内も随時行っている 。
1.2 積極的な子育て・母子保健支援制度
太宰府市は、妊娠期から育児期にかけて包括的かつ継続的な支援体制を構築している。特に、市が実施する「妊婦等包括相談支援事業」(旧:伴走型相談支援事業)は、単発の経済的給付に留まらず、行政が妊娠・出産・育児の各段階において相談を通じて継続的に関与する体制を構築しているのが特徴である 。これは、特に初めての子育て世帯や、多岐にわたる行政手続きに不慣れな新住民が、必要な支援を確実に受けられるようにするための重要な安全弁として機能している。
1.2.1 妊娠・出産に関する財政的・実務的支援
妊娠・出産に関連する財政支援として、「妊婦支援給付金事業」(旧:出産・子育て応援給付金事業)が実施されている 。この給付金は、妊娠期および出産・育児期における経済的・相談的支援を提供するものであり、利用には申請書交付、提出書類の準備、および支給額・回数に関する詳細(市の規定による)の確認が必要となる 。
また、出産の費用については、「出産育児一時金(家族出産育児一時金)」が適用され、1人の子どもにつき50万円が支給される制度である 。さらに、妊婦健康診査費用については、国からの助成制度が存在する 。出産後の心身の回復と育児をサポートするためには、「産後ケア事業」が用意されており、産後ケア施設の開設にかかる費用補助や、利用者向けの相談窓口も設置されている 。これらの制度に関する問い合わせ先は、子育て支援課母子保健係(電話: 092-555-6781)である 。
1.2.2 児童福祉と医療制度
子育て支援の根幹である「児童手当」は、出生届の提出と同時に申請することが強く推奨される 。この迅速な申請手続きは、給付の遅延を防ぐための行政側の配慮である。
加えて、市は「子ども医療制度」に関する最新情報(2025年7月17日更新)を提供しており、子どもの医療費助成に関する詳細を確認できる 。特殊な状況にある子どもへの支援として、「特別児童扶養手当」や、低体重で生まれた子どもを対象とする「未熟児養育医療給付制度」も整備されている 。教育・保育の面では、幼児教育・保育の無償化が推進されており、幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の利用、および認可外保育施設等を利用する子どもの保育料無償化には、それぞれ所定の手続きが必要となる点に注意が必要である 。
1.2.3 子育て支援施設の利用
地域の子育て支援の拠点として、太宰府市立子育て支援センターが市民に開放されている。所在地は太宰府市五条3丁目7-1で、連絡先は092-919-6001である 。また、子育て支援課が所管する「ぽかぽかサロン(子育てサロン)」も開設されており、親子の交流や育児に関する情報提供の場となっている 。
太宰府市における主要な子育て関連給付・手当
| 制度名 | 概要 | 主な支給額/助成内容 | 申請窓口 |
| 児童手当 | 児童を養育している者への手当 | 所得に応じて支給(要確認) | 子育て支援課 |
| 出産育児一時金 | 出産の費用補助 | 1人の子どもにつき50万円が支給 | 市区町村児童手当担当 |
| 妊婦支援給付金 | 妊娠・子育てを応援する給付金 | 支給額・回数は市規定による | 子育て支援課 母子保健係 |
| 産後ケア事業 | 産後の心身回復と育児サポート | 施設利用等に費用補助 | 相談窓口(子育て支援課) |
第2章:ごみ処理と資源リサイクルガイドライン
太宰府市のごみ処理は、福岡都市圏南部環境事業組合が管轄しており、環境保全とリサイクル推進のため、厳格な分別ルールと排出手順が定められている 。
2.1 ごみ出しの基本ルールと6分類の概要
ごみは太宰府市のごみ専用袋で出す必要があり、排出時間は夕方から午後10時までと厳守が求められる 。この時間指定は、衛生管理と集積所の維持を目的とした措置である。排出量についても制限があり、原則として1回につき
1世帯2袋までだが、収集休み明けや除草作業に伴う排出時には5袋まで出すことができる 。
2.1.1 家庭ごみ6分類と指定袋の色
太宰府市の家庭ごみは、以下の6種類に分別することが義務付けられており、特に指定袋の色で分類が区別されている。
- もえるごみ: 赤色の指定袋を使用し、収集は週2回である 。
- もえないごみ「ビン・缶」: 緑色の指定袋を使用し、収集は月に2回である 。収集曜日は地域によって細かく定められており、例えば石坂、宰府地区の一部では木曜日や月曜日に設定されているなど、複雑なスケジュールとなっているため、居住地域のカレンダー確認が必須である 。
- もえないごみ「その他」: 透明の指定袋を使用し、収集は月に1回である 。
- ペットボトル・白色トレイ: 黄色の指定袋を使用し、収集は月に1回である 。リサイクルの観点から、再生PET樹脂リサイクル推奨マークや牛乳パック再利用マークなどが付された製品の分別が奨励されている 。
- 粗大ごみ: 指定袋は不要だが、専用のシールを貼付する。収集は月に1回である 。
- せん定枝: こちらも専用シールを貼付する。収集は週に1回である 。
2.1.2 再生資源物(古紙・古布)の扱い
古紙(新聞紙、雑誌、ダンボール)と古布は、行政の収集による家庭ごみとして出すのではなく、地域コミュニティが主体となって実施する資源物回収に協力することが推奨される 。市は、資源物回収に協力する団体に奨励金を支給しており、地域の高いリサイクル意識を反映している。
2.2 粗大ごみ・せん定枝の処理手続きと費用(予約必須)
粗大ごみとせん定枝の処理は、他のごみとは異なり、事前の予約と専用の処理シールの購入が必須である。処理費用は、「粗大ごみ・せん定枝シール」(1枚500円)を貼付することで支払われる。シールは市内のスーパーやコンビニエンスストアなどで販売されている 。
- 粗大ごみ(月1回収集): ごみを排出する5日前までに予約が必要である。予約日数のカウントには、土・日・祝日・ごみ収集休みは含まれないため、余裕を持った手続きが求められる 。予約先は粗大ごみ受付電話番号( 092‐920‐2156)である 。
- せん定枝(週1回収集): 毎週収集されるせん定枝についても予約が必須であり、毎週月曜日の16時までに予約を完了させる必要がある。月曜日が祝日の場合は、原則として火曜日の午前中までに予約を行う。予約先はせん定枝受付電話番号(092-924-0899)であり、粗大ごみとは異なる専用の番号である 。
考察: 粗大ごみとせん定枝で予約電話番号が分かれていることや、予約期限が「5日前」と「毎週月曜16時」で異なる点は、住民が混乱しやすいポイントである。これは、処理施設の負荷分散と効率的な回収ルート管理を目的とした、行政による厳格な運用体制を示している。新住民は、居住地域の「家庭ごみの正しい出し方・ごみの持ち出しカレンダー」をダウンロードし、ルールの事前確認を徹底することが、円滑な生活の第一歩となる。
太宰府市 家庭ごみ分別・収集概要
| 分類 | 指定袋の色 | 収集頻度 | 予約要否 | 特記事項 |
| もえるごみ | 赤 | 週2回 | 不要 | 夕方〜午後10時までに排出 |
| もえないごみ (ビン・缶) | 緑 | 月2回 | 不要 | 地域別カレンダーを確認 |
| もえないごみ (その他) | 透明 | 月1回 | 不要 | 地域別カレンダーを確認 |
| ペットボトル・白色トレイ | 黄色 | 月1回 | 不要 | リサイクルマークを確認 |
| 粗大ごみ | シール貼付 (500円/枚) | 月1回 | 必須 | 5日前までに予約 (092-920-2156) |
| せん定枝 | シール貼付 (500円/枚) | 週1回 | 必須 | 毎週月曜16時までに予約 (092-924-0899) |
不用品回収 出張処分 引取り福岡パートナー
092-558-4380
住所:福岡県那珂川市今光4-110
私どものモットー業務上、ゴミを取り扱うことが多いため特に身なりには気を付け迅速に丁寧に清潔に対応いたします
第3章:交通アクセスと生活インフラ
3.1 交通システム:市内移動と広域アクセス
太宰府市は、西鉄太宰府線を中心とする鉄道網と、コミュニティバスを組み合わせた交通システムを有している。
市内交通
コミュニティバス「まほろば号」は、市民の日常的な移動や、太宰府天満宮から宝満宮竈門神社への移動(約10分)といった観光地間のアクセスにも利用されている 。
広域アクセス
福岡都心への主要なアクセスルートは、西鉄太宰府線「太宰府駅」を起点とする。福岡(天神)駅へ向かう場合は、西鉄大牟田線「二日市駅」での乗り換えが必要であり、概ね30〜40分程度の所要時間となる 。一方で、博多バスターミナルへは直行バス「旅人」が運行されており、こちらは乗り換えなしで約45分で到達可能であり、博多エリアへの利便性が確保されている 。太宰府市は観光都市としての側面が強いため、市民は観光客と共存する環境にあるが、文化・スポーツ施設が充実しており、市民の生活の質向上に寄与している。
3.2 市民が利用できる公共施設・スポーツ施設
太宰府市には、市民の健康増進や文化活動を目的とした公共施設が充実している。
- 体育・スポーツ施設: 太宰府市体育センター(電話: 092-921-0180)、太宰府歴史スポーツ公園(電話: 092-921-1132)、大佐野スポーツ公園、そしてとびうめアリーナ(太宰府市総合体育館)などが利用可能である 。
- 文化・学習施設: プラム・カルコア太宰府(中央公民館)、いきいき情報センター(太宰府市五条3-1-1)、男女共同参画推進センタールミナス、太宰府市文化ふれあい館(電話: 092-928-0800)などがあり、生涯学習や交流の場を提供している 。
3.3 生活インフラの緊急連絡先(治安)
市民の安全確保のため、警察による地域に密着した活動が重要である。太宰府市内の主要な交番の連絡先は以下の通りである 。
- 太宰府交番: 住所 宰府3-1-27、電話番号 092-924-4110。
- 水城交番: 住所 坂本1-5-45、電話番号 092-925-7265。
水道、下水道、ガスなどの生活インフラに関する緊急連絡先については、太宰府市役所の関連部署または管轄会社へ確認が必要である 。
第4章:医療・救急体制ガイド(筑紫地区連携)
太宰府市の医療体制は、筑紫医師会を中心とした広域連携モデルに基づいており、近隣市(筑紫野市、春日市)の大規模な総合病院との連携により、高度な救急医療サービスを確保している。住民は、緊急時にこの広域連携の構造を理解し、適切な手順を踏むことが重要である。
4.1 休日・夜間救急医療の利用手順と相談窓口
緊急時、特に夜間や休日の診療に関しては、以下の電話相談窓口を優先的に利用すべきである。
- 救急医療情報センター / 福岡県救急医療電話相談: 受診すべきか迷った場合や、適切な医療機関が分からない場合に相談できる窓口である。電話番号は**#7119または092-471-0099**であり、この窓口を通じて、時間的損失を防ぎながら適切な病院へ誘導を受けることが可能となる 。
- 小児救急医療電話相談: 15歳未満の子どもの急病に特化した相談窓口であり、電話番号は**#8000**である 。
- 休日・夜間当番医の確認: 当番医は日々変更される可能性があるため、受診前には必ず最新情報を確認することが必要である 。確認手段としては、市ホームページ、消防署(電話: 092-584-1191)、または市役所(電話: 092-501-2211)が案内されている 。筑紫医師会も定期的に「休日・夜間当番医表」を掲載している 。
4.2 筑紫地区広域連携による救急対応
太宰府市を含む筑紫地区5市では、医療機関が連携し、小児救急を含む広域での救急医療体制を整備している 。
- 広域対応の主要病院: 福岡徳洲会病院(春日市)や済生会二日市病院(筑紫野市)などが、内科・外科の休日当番医として対応実績があり、太宰府市民の急患を受け入れる体制となっている 。
- 小児救急体制: 小児科開業医と福大筑紫病院、徳洲会病院が協力し、独自の小児救急体制を構築している。福大筑紫病院では、[夜間診療](月・水・金/17時00分~21時30分)および[休日診療](9時00分~21時30分)を実施し、以降は救急診療部が対応する 。
考察: 太宰府市の医療体制は、近隣の大型病院との連携を前提としているため、住民は緊急時には直接地元のクリニックへ向かうのではなく、必ず電話相談を通じて適切な連携病院へ誘導されるプロセスを踏むことが、迅速かつ適切な治療を受けるための重要な行動原則となる。
太宰府市 救急医療・電話相談窓口
| 窓口種別 | 電話番号 | サービス内容 | 最優先の利用対象 | 備考 |
| 救急医療電話相談 | #7119 (または 092-471-0099) | 受診相談、医療機関案内 | 全年齢(緊急度判断) | 24時間対応(概ね) |
| 小児救急医療電話相談 | #8000 | 小児の急病時の相談、受診判断 | 小児 | 医療機関受診を迷ったとき |
| 消防署 | 092-584-1191 | 休日当番医の確認、緊急時の対応 | 全般 |
Google スプレッドシートにエクスポート
4.3 日常的な医療機関の検索
日常的な診療が必要な場合の医療機関については、筑紫医師会が太宰府市内の診療所・病院情報を提供している 。例えば、吉田皮ふ科形成外科クリニック(五条2-23-6)や渡辺整形外科クリニック(五条2-5-20)といったクリニックが市内に存在する 。また、福岡の医療情報ネットワークである「とびうめネット」も情報提供を行っている 。
第5章:防災・安全対策と緊急時対応
市民の安全確保の基盤として、防災情報へのデジタルアクセス、避難所の正確な理解、そして日常的な安全対策が重要となる。
5.1 防災情報のデジタル化とアプリの推奨
福岡県は、デジタル技術を活用した防災情報提供を強化しており、市民は以下のアプリを積極的に活用すべきである。
- 推奨アプリ:「ふくおか防災ナビ・まもるくん」 このアプリは、気象警報・特別警報、線状降水帯情報、土砂災害警戒情報、地震・津波情報、避難情報、避難所の開設・混雑情報など、多岐にわたる緊急情報をリアルタイムで配信する 。また、安否確認機能や透析医療機関被災情報なども備えている 。利用に際しては、位置情報の許可、マイエリアの設定、プッシュ通知の許可が必須設定である 。アプリは2022年12月23日から配信されており、Android 8.0以降、iOS 11.0以降に対応している 。
5.2 太宰府市指定の避難所・避難場所の構造
太宰府市では、災害の種類や緊急度に応じて避難施設を明確に分類している。
- 指定緊急避難場所: 災害の危険が差し迫った際に、緊急的に命の安全を確保するために使用される場所である(例:校庭などのオープンスペース) 。学業院中学校校庭、水城小学校校庭などが該当する 。
- 指定避難所: 避難者が一定期間滞在し、生活に必要な支援を受けられる施設である 。プラム・カルコア太宰府(中央公民館)、学業院中学校、水城小学校などが指定されている 。
- その他の避難施設: 都府楼共同利用施設、いきいき情報センター、太宰府館、各種公民館(連歌屋、馬場、新町など)も避難所として指定されており、特に一部の公民館は土砂災害時の避難所としても機能する 。
考察: 避難所には、緊急時の退避場所(緊急避難場所)と長期滞在可能な生活拠点(指定避難所)という明確な機能差が存在する。市民は、この二重構造を理解し、「ふくおか防災ナビ・まもるくん」アプリが提供するリアルタイムの危険情報(線状降水帯や土砂災害警戒情報)に基づいて、その時点で最適な避難行動をとる必要がある。
太宰府市 指定避難所および避難場所
| 施設名称 | 指定種別 | 機能概要 |
| プラム・カルコア太宰府(中央公民館) | 指定避難所 | 長期滞在可能な生活拠点 |
| 学業院中学校校庭 | 指定緊急避難場所 | 緊急時の安全確保(オープンスペース) |
| 学業院中学校 | 指定避難所 | 長期滞在可能な生活拠点 |
| 水城小学校校庭 | 指定緊急避難場所 | 緊急時の安全確保(オープンスペース) |
| 水城小学校 | 指定避難所 | 長期滞在可能な生活拠点 |
| いきいき情報センター | 避難所 | 公共施設を活用した避難場所 |
5.3 日常的な安全対策
災害時だけでなく、日常的なリスクへの備えも重要である。冬季、特に気温がマイナス4度以下になると、水道管や給湯管が凍結しやすくなる 。水が凍結すると体積が増加し、水道管の破裂や漏水を引き起こす可能性がある。平成28年1月には福岡を襲った寒波により多数の漏水が発生した前例があるため、特に北側や風当たりの強い場所で露出している水道管・給湯器には、保温材を巻くなどの防寒対策を講じる必要がある 。
第6章:生活の質向上と地域情報
6.1 地域活動と文化施設利用
太宰府市では、市民の健康維持や文化活動のための施設が充実している。太宰府市体育センターや太宰府歴史スポーツ公園といった施設は、日常的な運動の場として活用されている 。
また、市は共生社会の実現に向けた取り組みを積極的に行っており、障がい者週間(12月3日~9日)を設定し、障がい者福祉への理解促進を図っている 。障がい者差別解消法に基づく「合理的配慮」の推進により、誰もが地域の中で自分らしく暮らしていけるまちづくりを進めている 。さらに、市はまちづくりに貢献した市民を表彰する制度(社会功労表彰、善行表彰、地域活動奨励賞など)を設けており、市民の自主的な地域活動への参加を奨励している 。
6.2 ライフイベント後の手続き
市民の皆様にとって重要なライフイベントの一つである「おくやみ(死亡)」に関する手続き情報についても、市公式ホームページの関連カテゴリから詳細を確認できる 。

◇プロフィール◇
●要らないもの片付けアドバイザーの私、久松がご相談に応じます。
●迅速・丁寧・清潔に対応いたします。
●長崎県出身 福岡の大学を卒業後、いくつかの仕事を経験し大手リサイクルショップに16年間勤務したのち『不用品回収 パートナー』を独立開業。
会社概要
社名 :パートナー
所在地 :福岡県那珂川市今光4-110
電話番号 :092-558-4380
事業内容 :・不用品回収・リサイクル(買取、販売)事業・遺品整理・生前整理・ネット事業
古物商許可証番:福岡県公安委員会 第901131610009
号
資本金 :500万円
洗濯機処分 出張回収エリア
福岡県内全域|福岡市内|春日市|那珂川市|大野城市|太宰府市|筑紫野市|小郡市|久留米市|朝倉市|糸島市|古賀市|福津市|宗像市|北九州市|飯塚市|田川市|粕屋郡|遠賀郡|その他地域
佐賀市|鳥栖市|基山町|上記エリアに記載のないエリアはお問合せください。
洗濯機回収事例

◆福岡市城南区南片江
◆全自動洗濯機(4.2kg)
◆お一人暮らしの方のお引越しに伴い不要となったため不用品回収依頼
◆実際に支払った金額:5000円(税別)
福岡パートナー 洗濯機処分お支払い料金一覧表
縦型洗濯機 4.2kg未満 4,000円
5.5kg未満 5,000円
6.0kg以上 6,000円
ドラム式洗濯機 7,000円
※メゾネットタイプのご自宅は対応できない場合もありますのでお問合せください。
過去のお問い合わせで一番多かったお客様からのご質問
Q.回収費用のほかに引取り当日に別途必要な費用はありますか?(追加料金を請求されることはありますか?)
A.お電話で提示した金額以外で回収当日に追加費用を請求することは一切ございませんのでご安心ください
私ども福岡パートナーはサービスをご利用いただいたお客様が安心してご依頼できるように料金は明確にお伝えいたします。お見積りを行ったスタッフが必ず当日、現地にお伺いすることで言った、言わないなどの不安をなくすようにしております。一度、ご利用いただいた方からもおかげさまで再度ご依頼を頂くこともしばしば。
福岡パートナーおすすめポイント!!
・洗濯機の不用品回収や買取を行っています。状態が良くて高年式、パナソニックや東芝などの国内一流メーカーの洗濯機は買取りができるため処分費用がかからない場合もあります。
・洗濯機の回収料金をホームページに明示しており、単品回収も可能です。
・福岡県全域に対応しており365日いつでも対応可能です。
・洗濯機以外の不用品がある場合、一括して片付けにも対応しています。
・口コミ高評価多数獲得!信頼おける業者を目指し誠実に対応いたします。
・業界最安値には絶対の自信がありますので他社様と比較検討をおすすめいたします!
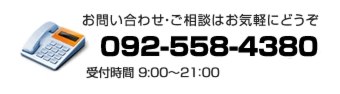



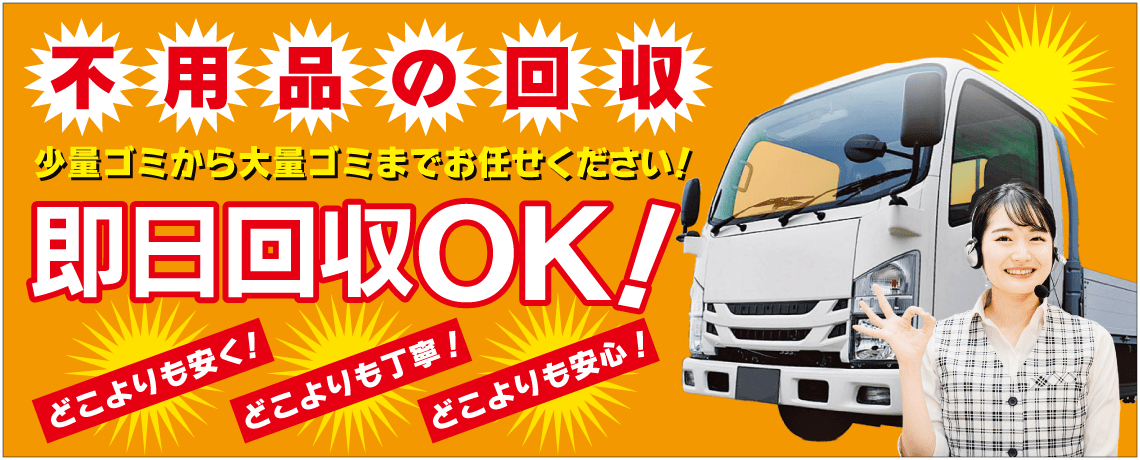

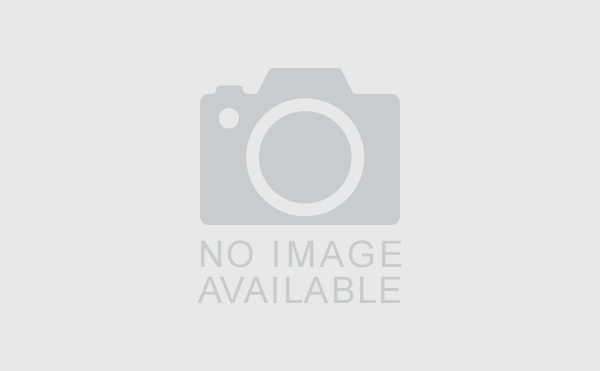
“太宰府市の生活に役立つ便利情報” に対して1件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。